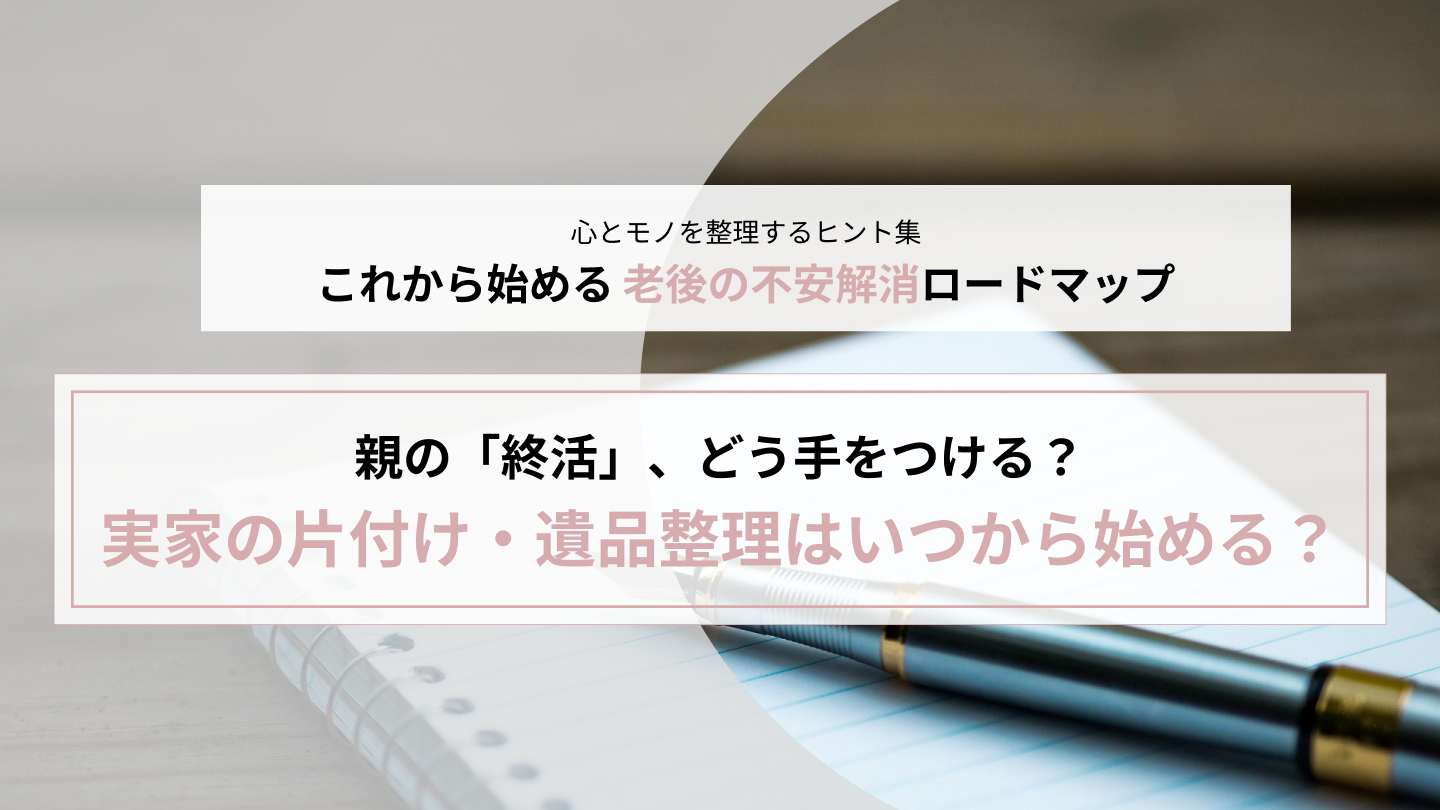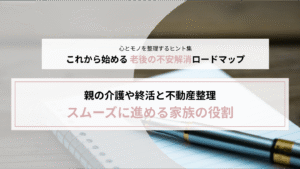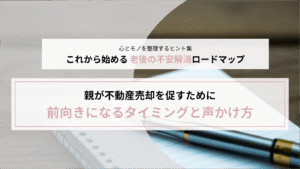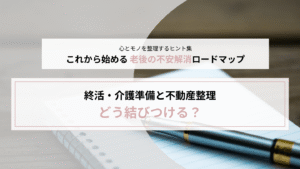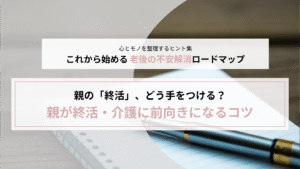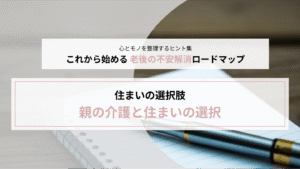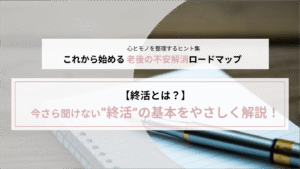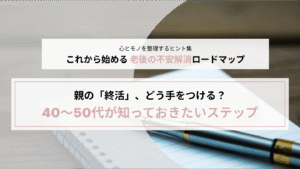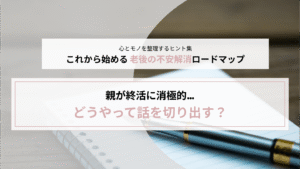親の実家や持ち家の片付け・遺品整理は、いつから手をつければよいのか悩む方も多いテーマです。「まだ親が元気だから大丈夫」と後回しにしているうちに、急に必要になって慌てることも少なくありません。実際には、早めに段階を踏んで整理を始めることで、家族の負担を減らし、親自身にも安心感を与えることができます。
遺品整理や片付けの準備は、単なる掃除や整理ではなく、家族の思い出や財産、生活に関する重要な情報を整理する作業でもあります。そのため、焦らずに計画を立て、効率的に進めることがポイントです。
片付け・整理を始めるタイミング
片付けや遺品整理を始めるタイミングとしては、親が元気なうちに「段階的に整理を進める」のが理想です。いわゆる生前整理を取り入れることで、親自身も物や思い出を整理しながら、自分の意思を家族に伝えられます。
ポイントとなるタイミングの目安
- 親が体力的・精神的に整理作業を行える状態
- 生活スペースに不要物が増え、日常生活に支障が出てきたとき
- 遺品整理や片付けの話題に親が前向きになれる時期
事前に少しずつ整理を進めることで、親も納得しながら物の取捨選択ができます。急に全てを処分するのではなく、まずは使わないものや記念品の整理など、小さなステップから始めることが大切です。
効率的に進める整理方法
整理作業は、ただ片付けるだけではなく「効率的に進める」ことが重要です。無計画に始めると時間も体力もかかり、親も疲れてしまいます。以下の方法を参考にするとスムーズです。
- カテゴリーごとに整理する
まずは衣類、書籍、思い出の品、日用品、家具などカテゴリーごとに分けます。カテゴリーごとに作業すると、進捗状況が分かりやすくなり、家族も効率よく作業できます。 - 使用頻度で分ける
「よく使う」「たまに使う」「使わない」で仕分けると、不要品の判断がしやすくなります。親自身に確認しながら判断すると、後悔のない整理が可能です。 - 写真や書類はデジタル化
思い出の品や書類は、デジタル化して保管するのがおすすめです。写真はスキャン、重要書類はコピーや写真で保存することで、物理的なスペースを減らせます。 - 処分方法を事前に確認する
家具や家電などは自治体の処分方法やリサイクル方法を事前に調べておくと、作業がスムーズです。粗大ごみやリサイクル品の引き取り日も確認しておくと安心です。
事例:生前整理で家族の負担を減らしたケース
ある家庭では、親がまだ元気なうちに生前整理を開始しました。衣類や書籍を整理する際、親が「思い出は残したいが、収納は増やしたくない」と考えていたため、不要なものを少しずつ処分し、必要なものは写真で記録しました。結果、親が亡くなった後の遺品整理はほとんど発生せず、家族の負担が大幅に軽減されました。
このように、親の意思に沿って段階的に整理を進めることで、家族の負担を減らしながら、親自身も安心して生活できます。
無理せず少しずつ進めることが大切
片付けや遺品整理は一度に全てを終わらせる必要はありません。親のペースに合わせて少しずつ進めることで、心理的な負担を減らすことができます。また、家族が協力して作業を分担することで、効率よく整理が進みます。
整理作業を進めるうえで心がけたいのは、親の思い出や感情を尊重することです。大切な品物や思い出を勝手に処分するのではなく、親の意思を確認しながら進めることで、家族間のトラブルも防げます。